反戦歌としてのブルーハーツ「リンダリンダ」
あまりに今更すぎるが、やっぱりブルーハーツが好きだ。ブルーハーツの曲には、差別的な歌詞が含まれているものもあって、手放しで賞賛したいというわけではないけど、反戦の歌を抵抗者の立場からいで、それを分かりやすい言葉に落とし込む技術が素晴らしすぎる。ブルーハーツは現代のアジテーターだと思う。
ブルーハーツの曲に直接的な反戦のメッセージが多く込められているのはよく知られている。たとえば、「ラインを越えて」にはこんな歌詞がある。
僕がおもちゃの戦車で 戦争ごっこしてた頃
遠くベトナムの空で 涙も枯れていた
は1962年生まれ。ベトナム戦争は1975年まで続く。曲の最後はこう締められる。
ジョニーは戦場へ行った 僕はどこにいくんだろう
真夏の夜明けを握りしめ 何か別の答えを探すよ
映画『ジョニーは戦場へ行った』は1971年。僕は戦場に行くのではない「何か別の答え」を探している。こうして「代わりの道」があると信じ、探し続けることに希望があると私は思う。権力が常に不当な二者択一を迫ってくるなかで、われわれはその選択肢を提示されること自体が不当であると訴え続けなければならない。『鋼の』で、アルは二者択一を捨てて「どちらも取る」道を探す。『進撃の巨人』で、ハンジはエレンに代わりの解決策を示なかったことを悔いる。高島鈴さんが書いていたコラムのタイトルは「There are many many alternatives」、「道は腐るほどある」だ。不当な二者択一に対する「代わりの答え」が見つからなければ、行きつくところは戦争とでしかない。われわれは、別の答えを探し続けなければならないし、その時に答えが見つからなくても、探し続けなければならない。
虐殺を生み出すメカニズムの一つである「差別」を、徹底して被差別者の側から描いたのが「青空」だ。
生まれたところや皮膚や目の色で
いったいこの僕の何がわかるというのだろう
「青空」が差別を歌ったものであることは誰でもすぐに分かるが、この曲の素晴らしいところは、して「抑圧される側」に視点が置かれていることだ。外見上の特徴や、国籍・アイデンティティなどの属性によって、その人のことを理解することはできない。外見や属性ではなく、その人の行動からしか、その人のことは判断できないはずだ。しかし、差別される者は、常に属性から中身を判断され続ける。
この歌詞の「この僕の何がわかると言うのだろう」というシンプルで切実な問いかけは、差別されてきた側からのものでしかあり得ない。差別されない者はその人の言葉や行為を受け止めてもらえるが、被差別者は属性で判断され、常に軽んじられている。一見、ストレートでよくある歌詞のように見えるものの、このことを分かりやすくシンプルな言葉に落とし込むのは、実は相当に難しいと思う。
たとえば、私が小学校の頃に流れていたアニメのエンディング曲の歌詞に、「世界が一つになるまで ずっと手をつないでいよう」という詞があったのを覚えている。これも平和を願った歌ではあるものの、「ずっと手をつないでいよう」という呼び掛けは、支配者からの言葉と捉えることもできてしまう。その場合、「ギャーギャー言ってないで仲良くしようぜ」という、被害者に対するとても暴力的なメッセージをもつ歌にもなりかねない。
しかし、ブルーハーツの歌はそういう方向の解釈になる可能性をに打ち消し、あくまで抵抗者としての言葉をいでいく。「が落っこちるとき」もそんな歌だ。
爆弾が落っこちる時 何にも言わないってことは
爆弾が落っこちる時 全てを受け入れるってことだ
爆弾が落っこちる時 僕の自由が殺される
爆弾が落っこちる時 全ての幸福が終わる
大人も子供も関係ないよ
左も右も関係ないだろ
こういう歌を作らなければならないのは、爆弾が落ちても何も言わない人が多すぎるからである。そして、何度も反対の意思表明がなされたきた歴史があるのに、歴史が何も変わらなかったからでもある。「青空」の最後の歌詞は、抵抗し続けた人、問いかけ続けた人の悲しさや絶望をよく分かっている人の言葉だと思う。
こんなはずじゃなかっただろう
歴史が僕を問い詰める
眩しいほど 青い空の真下で
こんなはずではなかった。こんなひどいことはもう繰り返されないはずだと、歴史は言っている。もう戦争も虐殺も起こるはずがない。でも現実はどうだろう。こんなはずではなかった、歴史がそうめてくるではないか……
さて、こういうことを考えて、改めてブルーハーツの代表曲の「リンダリンダ」を聴くと、これも反戦歌として解釈できることに気が付く。リンダリンダは、一般的には、「リンダ」という人に宛てて歌ったラブソングだと理解されているらしい。解釈は自由であり、そう解釈することで救われる人もいると思うし、その解釈も否定しない。ただ、以上の文脈を踏まえると、違う意味を持って現れてくると思う。
もしも僕が いつか君と 出会い 話し合うなら
そんな時は どうか愛の 意味を 知ってください
私にはこの歌詞が、いままさに戦車や爆撃機にされ、されている土地の人が、そのに向けて必死に呼びかけている歌として響いてくる。敵同士の僕とあなたが、戦場ではないどこかで出会うかもしれない。その時には「話し合う」から(=コミュニケーションを試みるから)、その前提として(つまり対話を成立させるための前提として)、「愛」を踏まえていてほしいという切実な願いが込められている。だから、
愛じゃなくても 恋じゃなくても 君を離しはしない
という歌詞は、異性愛強制でもなく、恋愛至上主義でもなく、もっとな人と人のつながりを歌っていると思う。敵国に分かれた二人の関係を恋愛に回収するフィクションがあるが、そうではなくて、愛でも恋でもなかったとしても、君を突き放しはしないから、話し合おうよ、と歌っているように思う。
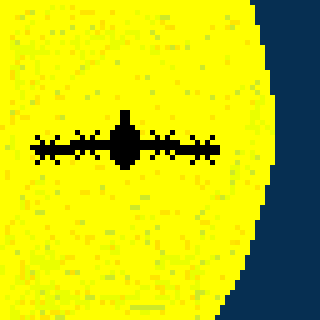
これは「敵と味方」的な世界観への抵抗としても読み取れる。そのことがよりはっきり表れているのが、「月の爆撃機」である。この歌は、爆撃機のパイロットと、爆弾を落とされる街の人の視点を切り替えながら進んでいく。
まず、「月の爆撃機」でかれる世界が、戦場そのものであるということ、つまり倫理や話し合いが通じない世界であるということが冒頭で示されている。
ここから一歩も通さない
理屈も法律も通さない
誰の声も届かない
友達も恋人も入れない
次の視点は街の人にある。
あれは伝説の爆撃機
この街もそろそろ危ないぜ
どんなふうに逃げようか
全ては幻と笑おうか
このまま、街の人から見た世界だけで歌詞を完結させてもよいところを、なめらかに視点が切り替わり、パイロットの視点が描かれる。
僕はいまコクピットの中にいる
白い月の真ん中の黒い影
そしてこの両者を「僕ら」としてまとめて、最後のブロックの歌詞が提示される。
いつでもまっすぐ歩けるか
湖にドボンかもしれないぜ
誰かに相談してみても
僕らの行く道は変わらない
人としての感情が置いていかれ、理屈も法律も通じず、相談しても変わらない世界の中で、まっすぐに歩き続けることができるのか。まっすぐ歩き続けたって、何も報われず、誰にも見向きもされず、湖に落ちてしまうだけかもしれない。街の人もパイロットも、そうやって作られてしまった世界のなのだ。誰かに相談したって未来は変わりそうにもない。歴史がそう言っている…。
この歌詞は、色々な意味で「戦地」に置かれる人の絶望と、その中でも手掛かりになるものがあること(薄い月明かり)を歌っているように思う。
以上の歌から分かるように、ブルーハーツの素晴らしいところは、一貫して、抑圧される者や支配に抵抗する者の視線から歌っていること、そして加害に加担する個人もまた、権力とシステムの犠牲者であるという視点を失わないことである。「TRAIN-TRAIN」でもこう歌っている。
弱い者たちが夕暮れ さらに弱い者たちを叩く
では、弱い者は叩かれるばかりで、残るものは絶望しかないのか? そうではない、とブルーハーツは歌う。なにせ、「その音が響き渡れば、ブルースは加速してゆく」のだから。悲しいことに、誰かに叩かれ殴られ踏まれたとしても、その「音」は、誰にも届いちゃいない。しかし、それを「響き渡らせる」ことができれば(より多くの人に届けることができれば)、ブルース(=抵抗の音楽)が加速していく可能性が開かれる。
ブルーハーツがいできたのは、まさにそういう音楽なのではないだろうか。以上、すごく当たり前のことを今更書いている気もするが、やっぱり書きたくなったので書いておいた。
