マーベルシリーズ「シャン・チー」の中国古代のたち
マーベルシリーズの「シャン・チー/テン・リングスの伝説」(原題:Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings、監督:Destin Daniel Cretton、2021年)は、過去のマーベルシリーズとは異なり、アジア、特に中国を舞台にしているのが特徴で、カンフーアクションや太極拳、マカオの街並み、鮮やかな神仙世界、柔らかな「気」の表現など、そこかしこに東洋を連想させる要素が込められている。
特に印象的なのが、最後の戦いの舞台となる仙界(といっていいのか分からないが、とにかく異世界的な場所)のシーン。主人公たちは、普段は閉ざされているがにだけ入り口が開く母の故郷の村(仙界)を訪れる。「」とは、先祖のお墓参りをする大切な祭日であり、この日は特別に村への通り道を開けるということなのだろう。そしてこの異世界には、独特な姿をした神々しい動物たちが生息している。
この仙界に登場するは、中国古代の神話に取材しているところが多い。中国古典での実際の記述を確かめながら、少し見ていくことにしよう。
帝江
本作の中盤、牢屋に閉じ込められた主人公たちが出会った役者のトレヴァーと戯れている謎の動物は「帝江」また「」と呼ばれるもの。作中で「顔はどこ?」と訊かれて恥ずかしがる描写があるのは、帝江のアイデンティティである「顔が無い」ことをよく表している。
およそ二千年前、漢代に作られたとされる『』という中国古代の地理書には、神仙や妖怪の類が色々と記録されており、ここに「帝江」の話も出てくる。
西方三百五十里には、「天山」という山があり、金と玉が多く、がある。英水がここから出て、西南に流れて湯谷に注ぐ。ここには神がいて、その形は黄色の袋のようで、煉丹の炎のように赤く、六本の足と四つの翼がある。渾沌としていて顔や目が存在せず、歌舞に詳しい。まことにこれこそが帝江である。
『』
役者であるトレヴァーと仲良しなのが、歌舞に秀でたとされる帝江というのは、偶然の一致かもしれないが、なかなかった設定であると言えよう。
『』は、各地の風土を記しながら、様々な不思議な逸話を伝える、なかなか扱いの難しい厄介な書で、それだけに後世の人々の想像を掻き立てたところも大きい。『』の記述から、イメージの膨らみを持った妖怪は数多い。
また、以下の『荘子』のエピソードも馴染み深いものである。
南海の帝を「」といい、北海の帝を「」といい、中央の帝を「渾沌」という。ととは、時おり渾沌の地で会い、渾沌はたいそう厚く彼らをもてなした。儵ととは、その渾沌の徳にお返しをしようと計画し、「人はみな七つの穴(目・鼻・口・耳)があり、それにより見て、聞いて、食べて、呼吸しているが、渾沌だけはこれがない。彼に穴をあけてみようではないか」と言った。そこで一日に一つずつ穴をあけると、七日目に渾沌は死んだ。
『荘子』内篇・応帝王
この逸話は、アイデンティティの名乗りによってその人のアイデンティティが失われることを象徴的に表現したものという解釈も可能で、深読みしがいがあるが、今はいておく。
早稲田大学の古典籍総合データベースに『』の絵入りの本があり、帝江の姿も描かれている(ただ、この絵はあくまで後世に想像して書かれたものではある)。この画像を見ると、映画に出てきていた「モーリス」にそっくりであることが分かる。
九尾狐
九尾狐は、異世界の村に入った時に最初に出迎えてくれる動物。その名の通り、九つの尾がある狐のことで、同じく『』に登場している。
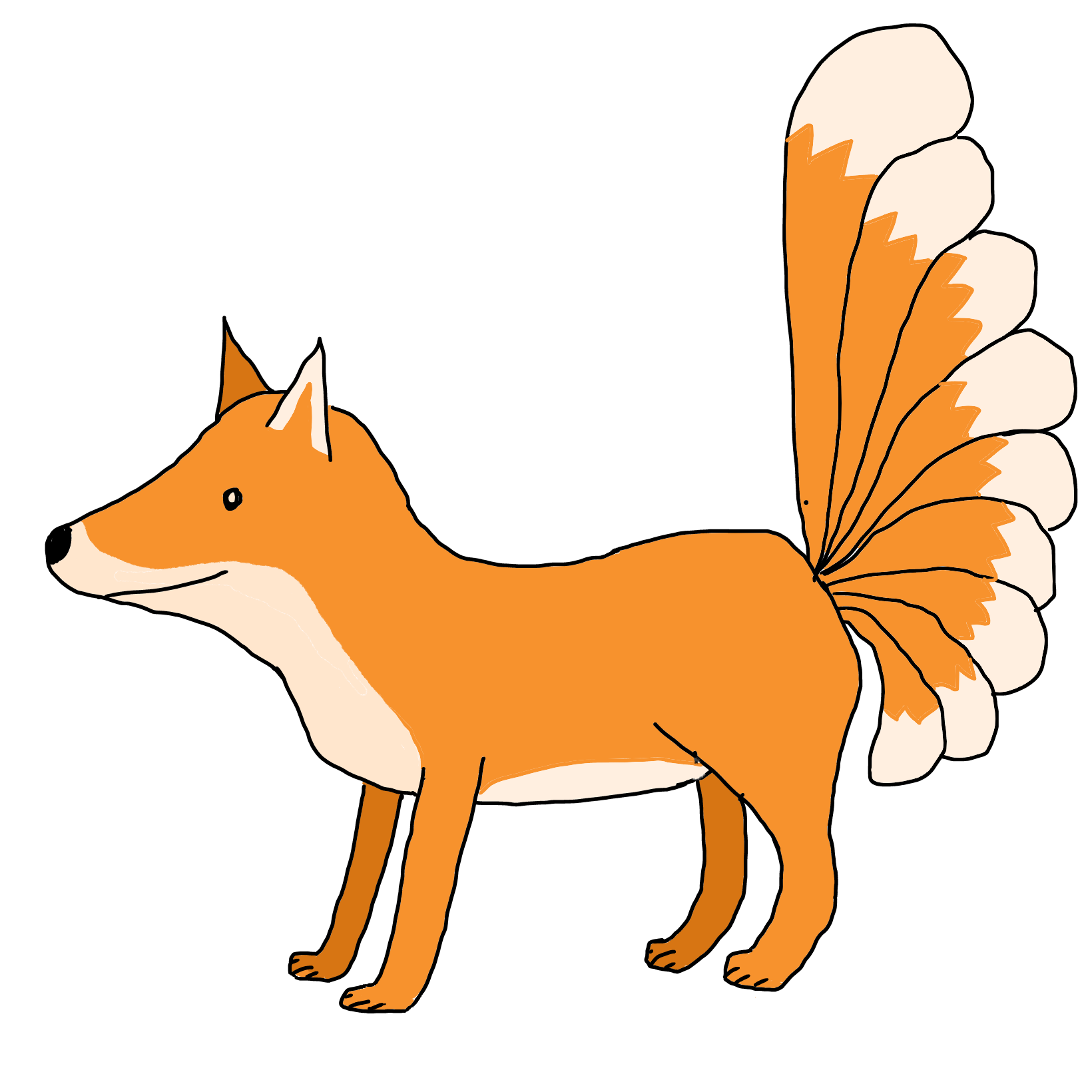
また東方三百里には、「青丘」の山があり、その南側には玉が多く、その北側には青(青色の宝石)が多い。獸がいて、その形は狐のようで九つの尾があり、その鳴き声は幼子のようで、人を食べることができ、食べたものは毒に当たらない。
『』南山経
ここには「人を食う」などと書かれてマイナスのイメージを持つかもしれないが、九尾狐は伝統的には瑞祥をもたらす獣とされ、例えば『』(後漢時代に政府で作られた、経書の統一理解を示す書)にはこうある。
天下が太平となるときに瑞祥が来る理由は、王者が統治を受け継ぎ、陰陽を調和させると、陰陽が和し、万物が秩序立ち、瑞祥の気が充満するから、瑞祥が来るのであって、いずれも(王者の)徳に応じてやってくるのだ。(中略)徳が至ると、鳥獣では鳳皇が飛来し、鸞鳥が舞い、麒麟が来て、白虎が来る。狐が九尾を持ち、白い雉が降りてきて、白い鹿が現れ、白鳥が下りてくる。
『』封禪
そして、なぜ九尾狐が瑞祥になるのかということを問答形式で説明したのが以下の部分。
「狐九尾とは何か?」「狐は故郷の丘の方に頭を向けて死に、自分の本源を忘れないので、安泰な中でも危険を忘れないことを明らかにするのだ。」「九尾でなければならないのか?」「九人の妃が自分の居場所を得て、子孫が増えることを表している。」「尾が九つなのはなぜか?」「後世に盛んになっていくことを明示しているのだ。」
本作は母の故郷を訪ね、自分のルーツに向き合うという話であり、「狐は故郷の丘の方に頭を向けて死に、自分の本源を忘れない」とされる狐にピッタリであると言える。
もちろん、先ほど紹介した絵入りの『山海経』でも登場している(右側の左上あたりにいる)。ほか、ポケモンの「キュウコン」やNARUTOの「」、アニメ「」の主人公の「九月」のモデルも九尾狐である。
麒麟
麒麟も、同じく主人公たちが仙界に訪れた際に、最初に出会う動物の一つ。キリンビールや大河ドラマの「麒麟がくる」などでお馴染みのである。
本作の麒麟たちは、主人公を見ても逃げることなく、意味深に目を向ける。麒麟は太平の世の訪れを示すの代表格であり(先の『』の引用箇所にも「麒麟」が出てきている)、これはシャン・チー一行が太平をもたらす存在として是認されていることを象徴する。一方で、その後に悪役である主人公の父が来た際には、麒麟は一目散に逃げだしている。ここは麒麟を用いて分かりやすい対比を作っているシーンである。
古来、麒麟の来訪はであり、太平の世がまもなくやってくることを示すものとされてきた。大河ドラマの「麒麟がくる」というタイトルも、明智光秀の死ののち、秀吉を経て徳川による太平の世が始まることを暗示するものである。麒麟が瑞祥として特に有名になった理由は、これが『春秋』という書物の末尾で描かれているから。伝統的に、孔子が編纂したとされて重視されてきた歴史書である『春秋』は、魯の哀公十四年(紀元前481年)の「獲麟」、つまり「麒麟を捕らえた話」で終わる。
『春秋』哀公十四年
「どうして(獲麟のことを)記録したのか?」「異常なことを記録するためだ。」「どうして異常と言えるのか?」「中国(中原地域)の獣ではないからだ。」「それなら誰がこれを狩ったのか?」「木こりだ。」「木こりは身分の低いものなのに、どうして(本来は天子に対して用いる)「狩」という語で書かれているのか?」「これを重要なものとするためだ。」「なぜ重要なものとするのか?」「獲麟が重要なことだからだ。」「なぜ獲麟は重要なのか?」「麒麟とは、仁獣である。王者がいればやって来て、王者がいなければやって来ない。孔子に報告に来た者が「(鹿の一種)に似て、角の生えた動物でした」と言った。孔子は「なぜ来たんだ!なぜ来たんだ!」と言い、袖で涙を拭い、涙が服を濡らした。顏淵が死ぬと、孔子は「ああ、天が私を滅ぼした」と言った。子路が死ぬと、孔子は「ああ、天は私を断じた」と言った。「獲麟」のときには、孔子は「私の道は窮まった」と言った。」
『』哀公十四年
この話は、孔子が当時の時代のことをどうとらえていたのか、という重大な問題と関連するため、長年経学者たちが議論してきた問題でもある。とにかく、孔子がこれだけこだわったとされる獣であり、議論の蓄積もで、中国として代表的な扱いを受けるようになった。
獅子
仙界の集落の両サイドで家を守っている動物。中国では、ライオンを象った石像(石獅子)を家の守護に置く風習があり、これが伝わって日本の狛犬や沖縄のシーサーなどが生まれたという説もある。日本では「唐獅子」などとも呼ばれる。
龍
仙界の守護神として立ち現れるのが「龍」。本作では龍が水底から現れてくるが、「龍」と「水」にイメージの重なりを見るのも中国古来の観念である。一例として、後漢の王充の『論衡』という本を観ておく。ここは、龍に関する当時の言説を王充が批判する一段。
盛夏の時、雷電が落ちて樹木を破壊し、家屋を破壊することを、俗に「天が龍を取る」という。これは龍が樹木の中に隠れていたり、家屋の間に隠れていたりして、雷電が樹木に落ちたり、家屋を破壊したりするのは、つまり龍が外に出現することであるから、龍が現れ、雷がそれを取って天に昇らせるのだ。世の中の愚昧な人々は、みなこの説が正しいと言う。しかし、よく考えてみると、これは虚妄の言である。
本当のところは、雷と龍が同類であり、両者が両者の気を感応させるものであり、だから『易』に「雲は龍に従い、風は虎に従う」というのだ。また、「虎が嘯くと谷に風が届き、龍が興ると空に雲が起こる」という。龍と雲とが呼び寄せ合い、虎と風とも呼び寄せ合うから、董仲舒が雨乞いの祭りの方法を定めた際には、土龍を作って感応を起こそうとした。
『論衡』龍虚篇
ここには、雨乞いの祭りの際に、龍を呼び寄せる儀式が行われていたという話が出てきている。これは龍と水が「同類」と考えられていたからこそ出てくる考え方と言える。これを同類相感といい、武田時昌『術数学の思考―交差する科学と占術』(臨川書店、2018)などに詳しい。
王充の『論衡』は当時の迷信を批判することが多いのだが、その王充でも、「龍を用いた雨乞いの祭り」が妥当なものという前提から論じているわけで、龍と水の結びつきの強さを物語っているろ言えよう。
まとめ
以上、「シャン・チー」に登場する中国古代のたちを紹介してきた。こうして見ると、映画内では一瞬の描写であっても、歴史的な文脈を踏まえて製作されていることが分かる。こうした細かいディテールの一つ一つを積み重ねて、隙の無い演出がなされた時に、統一的な世界観が生み出されてくるのだろう。
